売れる製品は「良い」製品。では「良さ」をどのように捕らえますか?<2018年10月30日>
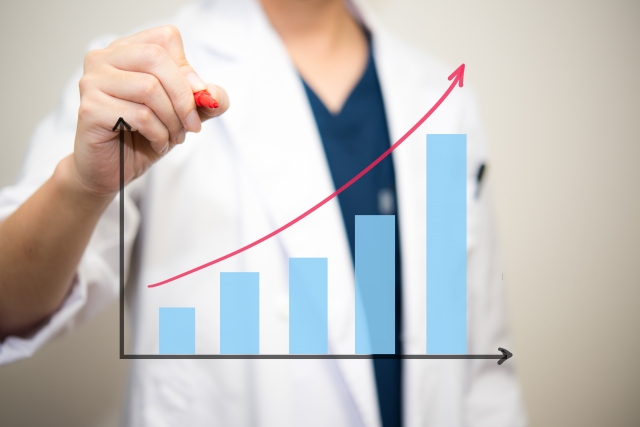
●売れるものを作りたい
日銀の低金利政策のおかげで、ものづくりの世界もやっとデフレから抜け出しそうになっているそうだ。でも、よく考えてみれば、値段を高く誘導して(インフレへ)、どうやって売るというのだろう。消費税が10%へ上がることが決まっているらしいから、値段が上がるというだけで売れなくなる可能性が高くなる。ちょっと前の円高のときに、いくら良いものを作っても、輸出では円が高くなりすぎて「価格競争力」がなくなったという経験があるから、「良いもの作れ」だけでは心もとなくなって、なんとかして「売れるものを作れ」と言われる。このような話はどこでも聞こえてくる。では、売れるものはどうやって作るのか?
こんな無理な質問をされることも多いのだが、官能評価に関わる身としては、そんな特効薬がないことは知っているし、何より現在の日本の市場はかなり成熟していて、それほど「欲しいもの」がなくなってきているのも生活実感として持っている。じゃぁ、官能評価流に考えると何ができるのか。私はまず、品質保証に官能評価が使えます、と説明することにしている。ここでの品質保証は、「ちゃんと作っています」という感じの言い方になる。
●市場に聞いてわかるのか?
市場が成熟していない段階では、「とりあえず作ってみて評判が悪ければ止めてしまえ」アプローチで行こう、というようなこともあったらしい。逆に、出してみて受けたからもっと作っていたら売れなくなってしまう、ということもある。このような試行錯誤は市場が拡大されて製品も市場も成熟する方向に向かうと、だんだん使えなくなる。どうやら市場が成熟するというのは、生活者側が「良いもの」かどうかわかってしまうということらしい。だから、良いものが増えてきたら選ぶ側は自分の欲しいものを選ぶようになる。例えば、インスタントコーヒー。パッケージングに気を使って、ブランド化のために努力した結果、「インスタントコーヒー」のパッケージにゴールド(金色)を使う製品は当初ほとんどなくて、スーパーの棚で目立っていたのに、すぐにゴールド競争が起きて、目立たなくなってしまう。そのような経験があるから、付加価値(パッケージ)ではなく、本来の製品の持っている「魅力」である「おいしさ」で勝負しようという方策をとっているらしい(そのために、インスタントコーヒーという名称自体も否定しようとした)。結局、嗜好性の高い飲料なのだから、一定以上の性能(おいしい)を持っていることへ戻って、改めてそれを市場へ訴えようとしているのである。これは高級路線とは少し異なる。材料を厳選したらどうしてもコストが高くなってしまうから、結果的に値段が高くなっても売れるだけの「良さ」を追求した結果だからである。まだ現在進行形の戦いが続いていて、値下げ競争(生活者のデフレ経験からの欲求)に巻き込まれそうになることへどのように対抗するか、個人的に注目している。(官能評価流にいうと、いわゆる本物の基準となる「レギュラーコーヒー」が存在しているのに、簡便性をうりにした「インスタントコーヒー」がどのように高価格帯で戦うのか、というこれまでの構図に、新しい技術で違う魅力(おいしさ)を与えようとしているように感じている。果たして切り口が違うと市場にアピールできるのか。)
●製品の良さは原材料の良さだから高くても良い?
原材料を厳選する、ということは、価格に確実に跳ね返る。肉を原料とするハム・ソーセージは、同重量の肉の原価よりも確実に高価になる。原料米を磨くことで味を追求するお酒(吟醸酒)は50%磨いてしまうと原材料が半分になることになる。「良い」製品ができて売れると、その量産技術が生まれ、模倣がおき、同じようなポジションの製品がより安価に溢れてくる。この時、最初に作られた「良い」製品の「良さ」とは、違うものになってしまいがちである。この変化を利便性とか簡便性といった「魅力」であるとして、従来は突破しようとしてきた。この現象が、市場が拡大して製品が認知されるようになる(とりあえず買ってみよう)ことなのか、製品の比較評価の中で「良さ」が認知されて製品が選ばれるようになる(これを、xxxだから買ってみよう)ことなのか、経過を分析しても、未来予測は難しい。なんせ、気まぐれな人間が相手だからである。
●人間相手の戦い方は?
人間の好みとは何か、これも官能評価のテーマの一つである。しかし、うまく行かないことの方が多いテーマでもある。その理由の一つが、「なぜ売れたのか(なぜ評価が高かったのか)」を好みだけで説明しようとするからである。ちょうど、魅力的品質だけで説明しようとしても、基本的な性能(当たり前品質)がダメだと話しにならない、ということに似ている。さらに、相手の人間が一人ではなく複数(いや、大集団)になってしまうと、好みの筋道はもっと複雑(好みは人の数だけ)になりかねないし、知見を整理して得られる方法論(同じ説明原理で説明できること)は、違いが少しだけの製品にも使えなくなることが起きる。そして、それがはっきりするのは、市場に出して「売れなかった」ケースになってしまってからなのである。
●好みをあてにしようとすると
官能評価では、好みは直接扱わない。その理由は、好みであることが評価が高い原因なのか、多くの人が「まあ、よかろう」とする機能と価格の幅に収まっているから、評価が高いのか、がはっきりしないからである。好みが合う製品があれば、少なくとも買ってくれるだろう、とは言える。ただし、値段の折り合いがつく範囲の製品だろうと予想される。では、また「売れるから好まれているのか」「好まれているから売れるのか」という話が出てきて先に進まない。だから、官能評価は好みを直接扱わない。まず、その製品の「良さ」を人間がどのように捕らえているかを考えるのである。
「良さ」は生活者側の視点である。作る側としては、その「良さ」を生むための生産のレシピを作らないといけない。何を増やせば「良さ」に効くかが分かればよいことになる。しかし、この「良さ」がまた面倒な評価になる。今なら、AIで大量のデータを分析して「良さ」を導くこともできるのかもしれない。しかし、それでは、「なぜ良いと判断したか」がわからないから、結局、「売れたものが良いものだ」ということと同じ方法論を取ることになる。また、そのレシピのどこを改良すれば、より良いものがうまれるかがわからない。これでは、時間をかけたわりに得られるものが少ないような気がする。
●製品を作るためにあてにするのは
というわけで、このようなアプローチからは、はっきりしないことがあまりにも多いため、官能評価では、当たり前の「良さ」からアプローチする。まず、その製品の「良さ」がどのように構成されているのか、これは、競合製品との比較評価の中ではっきりする。だから、まず、「良さ」を調べて、それを指標化することを考える。しかし、最終的にレシピを作るのだから、評価をする人間側だけの意見を聞いていると混乱するだけである。そこで、官能評価では、レシピ(物理量)を人間側がどのように受け取るのかという感覚の測定を行う。この物理量と発生する感覚量との対応関係を探ってきたのが、これまでの官能評価の研究の歴史なのである。人によって好みは違うのかもしれないが、人だから物理的な刺激を与えると、必ず感覚が生じる、その感覚を測定する方法を探究してきたとも言えるのである。
冒頭の「ちゃんと作っていますよ」が品質保証というわけは、人間相手で限定されるはなしである。基本的な商品特性を人間側が評価できるようになっていて、物理的な刺激がどのような感覚を生じているのか、ということが官能評価の研究の第一歩である。その中で、メカニズムがはっきりしたら、知見として転用できることもある。今でも工場の最終ラインで、熟練工が出荷検査をしているかもしれない。そのメカニズム(合格不合格)がはっきりしたら、機械化へと進むかもしれない。これがセンサーとして使われる多くの現場で起きたことなのだが、人間相手の製品としては、物理量を感覚量としてどのように捕らえているか、というメカニズムの解明の繰り返しだったのである。
というわけで、無理な質問をされたとき、逆に「どんな物理量と感覚量の対応が基礎になっているか」を聞きたいのです。それがはっきりしているのなら、比較的楽な作業かもしれないから。でも、この基本的な枠組みがとらえきれていない製品が多いようなのだ。

井上 裕光
(千葉県立保健医療大学)
愛媛県生まれ。東京都立大学人文科学研究科心理学専攻博士課程単位取得退学。現在、千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科教授。1990年より(一財)日本科学技術連盟官能評価セミナー運営委員長。1995年より日本官能評価学会常任理事。JIS官能評価分析策定に作業部会として関わり、2003年よりISO/TC34 SC12(官能評価)国内対策委員。2010年専門官能評価士。
専門分野は、心理学(発達心理学、数理心理学、データ解析)、官能評価分析、人間工学(ヒューマンインタフェイス)、教師教育などで、人間が評価すること全般に関心がある。






