製品のデザインプロセスをデザインする<2015年10月09日>
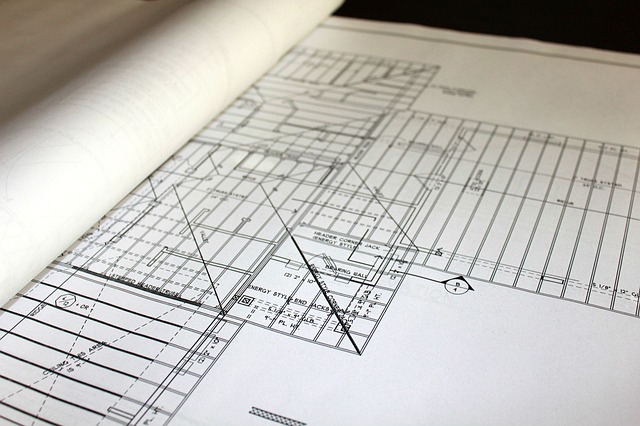
日本では、「デザイン」という言葉に対して、物の造形・形状や色彩などを作り込むこと、というイメージが強かったと思われます。たとえば80年代には「DCブランド=Desiner's & Character's Brand」という言葉が流行しました。渋谷のParcoや丸井、non-noやan・anなどの言葉とともに、懐かしく感じる方も多いかもしれません。ここでいうデザイナーとはファッションデザイナーの事であり、もしかしたらこうしたところから、先に示した形状や色彩といったイメージとデザインという言葉が強く結びついたのかもしれません。
しかし、近年では「デザイン」という単語の意味、定義が見直されているようで、より幅広い意味を持つようになっています。モノの形状・色彩の設定から、製品の持つ問題の解決や機能、コンセプトづくりまでを含めてものづくりに関わっていく、いわゆる企画や開発、設計までを含めてデザインという言葉でくくっています。英単語での“Design”では「下絵を描く、設計する」という意味も含んでいますので、そういった意味では、そもそもの言葉の意味合いに近づいている、という考え方もできるのかもしれません。
さて、前置きが長くなりましたが、ここでお話ししたいのは製品のデザインの話ではなく、製品の設計プロセスのデザイン、というお話です。
ものづくり、特に製造は、インプット-プロセス-アウトプットの関係で語られます。原材料や部品などをインプットとし、それを製造プロセスで加工し、アウトプットとしての製品(完成品)が誕生します。そのプロセスを造り込むことは、生産効率や製品品質に大きく関わってくるのは周知の事実です。そのため、生産プロセスは、極力ムダを省きつつ、効率よく、機能的になっていることが望ましいとされます。そして、それは製品のデザインプロセスにも同じ事が言えます。

図1.インプット-プロセス-アウトプットの関係
製品のデザイン・設計においては、さまざまなユーザーの情報などをインプットに、それを検討し、設計として創り込むことで、アウトプットとしての製品設計・デザインを導き出します。では、その設計・デザインのプロセスはどうあるべきか、ということです。
もちろん、製品ごとに生産プロセスが異なるように、同じ設計という言葉でも、業種や製品が違えば最適解も異なります。考えるべきは、インプットとしてどのような情報があるのか、アウトプットとしてどのような設計の品質が求められるのか、そしてそれを実現するためにどのようなプロセスが必要なのか、という視点です。あるいは、生産工程を繋ぎ合わせるように、どのような設計工程を、どう繋いでいくのが良いのか、とも言い換えられます。
顧客の要求や、持っている問題・課題の整理、実現すべき機能の選択、あるいは技術課題の抽出と解決、品質の保証などなど、やるべき事はたくさんあります。これらについて、それぞれの目的や機能、個別の入出力などを考慮し、対応する適切な手法をうまくつなげていくことが肝要と言えます。最近はそういった設計開発に関する手法-QFDやTRIZ、タグチメソッド、人間中心設計、SNマトリクスなど-の連携に関する事例なども見られるようになってきましたので、それらを参考にするのも良いかと思います。
良い製品は、良い設計・デザインによって実現されます。そして、よい設計・デザインは、よいプロセスによって創られるのです。
日科技連事務局






