未然防止とは―vol.2ー<2021年07月30日>

先回、未然防止はカップの黄色い部分の問題を発見することだと説明しました。カップの黄色い部分とは、お客様の期待と与えられた目標のギャップです。ここには設計担当者は気づいていないのですから、それに気づく、発見するというのが、未然防止の第一歩になるのです。
そこで筆者はCOACH法という発想法を作り、それを使うことにしました。COACHとはC: Concentrating, O: Objective, A: And, CH: Challenging を合わせたもので、良い発想のためには、集中する/客観視する/良いイメージを持ってあきらめないことが大切だということです。そして、そのうち「集中する」をGood Dissection(現地現物)と「客観視する」をGood Discussion(ワイガヤ)とし、それにGood Design(差に着目した設計)を加えてGD3という手法を作りました。日本語で言うと「サ・ワ・ゲ」と言うことになります。
設計者は目標達成を目指してカップの青いところを仕上げるでしょう。しかし、カップの黄色いところに潜む潜在問題には気づいていません。その潜在問題をレビューアーが発見して設計者を助けると言う手法を作り上げたのです。それがDRBFM(Design Review based on Failure Mode)です。さらに、試験後のデータの変化点に着目して、そこに潜む潜在問題を引き出すのがDRBTR(Design Review based on Test Result)、二つのものを直接比較して、差に着目して潜在問題を発見するのがDRBDP(Design Review based on Difference of Products)です。
これらは潜在問題を発見するための手法で、ワークシートを綺麗に書いたからといって潜在問題が発見できるわけではないのです。よく「DRBFMを作りました」と言う人がいますが、それは全く誤りです。「帳票を与えられたら、それを埋めればいい」と言う、学生時代に鍛えた「穴埋め体質」の現れです。帳票はレビューアーが問題を発見するために、レビューアーに設計を理解してもらうために行う設計者のサービスなのです。大切なことはレビューの場でサ:差に着目して、ワ:ワイガヤとゲ:現地現物で潜在問題を発見することなのです。つまり潜在問題を発見する責任はレビューアーにあるのです。
つまり、レビューアーの「発見力」が決め手になります。もちろんその潜在問題に対する専門性が必要だとも言えますが、そもそも潜在問題ですから、どの専門性が必要なのかはわからないことが多いのです。設計者とは別の視点で、設計を見てもらうことが大切で、同じ分野の設計者(仲間内)が集まって実施しても発見力は高まりません。設計を理解してもらう上でも、後工程を担う人たちが参加することが必須です。そのほかいくつかのコツを「発見力」講座で披露します。
★関連記事★
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【第1弾】未然防止とは ーvol.1ー
https://www.juse.or.jp/src/mailnews/detail.php?im_id=150
【第3弾】未然防止とは ーVol.3ー:未然防止の考え方を問題解決に繋げる
https://www.juse.or.jp/src/mailnews/detail.php?im_id=153
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
- 未然防止・問題解決のプロセスマネジメントに役立つ「発見力」強化セミナー
- 設計・開発における未然防止手法セミナー ~日産式Full Process DRとQuick DR~
- 設計・開発における未然防止手法デザインレビュー レビューア育成セミナー
- 多様な知識を統合する技術の学習と実践の講座:デザインレビュー
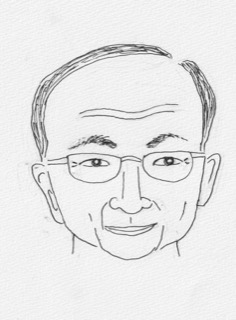
吉村 達彦(よしむら たつひこ)
1968年 トヨタ自動車工業(現・トヨタ自動車)入社
1988年 工学博士(東北大学)
強度実験課長・シャシー技術部長・信頼性強度機能主査等を歴任
2000年 九州大学 大学院工学研究院機械科学部門固体力学講座教授
2003年 General Motors Executive Director Reliability & Durability Strategy
2007年 ジーディーキューブコンサルティング代表
【受賞】
•自動車技術会論文賞
•機械学会技術貢献賞
•日経品質管理文献賞
【著書】
『トヨタ式未然防止手法GD3』(2002)日科技連出版
『想定外を想定する未然防止手法GD3』(2011) 日科技連出版
『想定外と言わない組織を作るAPATマネジメント』(2012) 日科技連出版
『発見力』(2016) 日科技連出版






