未然防止とは―vol.3ー:未然防止の考え方を問題解決に繋げる<2021年08月05日>

■未然防止の考え方を問題解決に繋げる
私たちはお客様や客先から不具合(品質問題)を指摘されると、自社の工程を見直して、決められた仕事が正しく行われていたのかどうかをチェックし、正しく行われていなかった工程を探し出して、それが原因だと言って、それをなおして、それを客先に決められた様式に従って報告し、一件落着とします。そして、その原因を作った人のヒューマンエラーだと言って、それを責めます。
一方では、個人の問題ではなく、マネジメントの問題だと言って、マネジメントシステムを見直します。マネジメントが正しく行われていることを示すために、色々な帳票ができ、それを埋めることが仕事になります。これは少し極端な言い方ですが、いずれにしても、決められた様式/帳票を埋めるのが私たちの仕事の大きな部分を占めているのは否めないでしょう。これを「穴埋め体質」と言います。「日頃の雑用のような問題解決などでは、そんなこともあるかもしれないが、本当にしっかりやらなければいけない問題解決では決してそのようなことはしていない」という人もいるでしょう。しかし、日頃やっていない、体に染み付いていないことが、本当に必要な時にできるのでしょうか。では、私たちの体に染み付いた「穴埋め体質」を払拭するにはどうしたら良いでしょうか。
筆者は未然防止に関連して、GD3(Good Design/ Good Discussion/ Good Dissection)という概念を提案しました。日本語で言うとサ:差に着目して、ワ:ワイガヤとゲ:現地現物になります。潜在問題を発見して未然防止を図る鍵なのですが、問題解決でも大切な視点になります。特に問題解決の初期に行う現状把握というプロセスをしっかり取らないで、いきなり対策や原因を決め打ちすることが、上記のような問題解決の要因になっています。そこで、このGD3を現状把握のプロセスに使い、それを対策までつなげる手法としてFPA(Failure Phenomena Analysis)という手法を提案しました。
問題解決の報告書の最初に、現状把握とか現品調査結果のような項目があります。多くはどんな問題かを説明しているだけです。イントロなのです。そして、たいていは問題解決の結論として、「メカニズム」の説明があります。問題に至るプロセスが示されています。それなら最初の現状把握の段階で、メカニズムをいくつか想定して、それを調査観察していくことによって加筆修正を加えていくことによって、最終のメカニズムに絞り込んでいくプロセスが問題解決だと言えるでしょう。
つまり、問題解決は現状把握の繰り返しということになります。それだけ大切な現状把握を私たちは疎かにしているのです。ここで、サ:差に着目して、ワ:ワイガヤとゲ:現地現物(徹底的観察)をどうやって組み合わせるかがコツになります。穴埋めでは最後のメカニズムに到達できないでしょう。穴埋め体質払拭のきっかけにもなればと思っています。
★関連記事★
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【第1弾】未然防止とは ーvol.1ー
https://www.juse.or.jp/src/mailnews/detail.php?im_id=150
【第2弾】未然防止とは ーvol.2ー
https://www.juse.or.jp/src/mailnews/detail.php?im_id=152
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
- 未然防止・問題解決のプロセスマネジメントに役立つ「発見力」強化セミナー
- 設計・開発における未然防止手法セミナー ~日産式Full Process DRとQuick DR~
- 設計・開発における未然防止手法デザインレビュー レビューア育成セミナー
- 多様な知識を統合する技術の学習と実践の講座:デザインレビュー
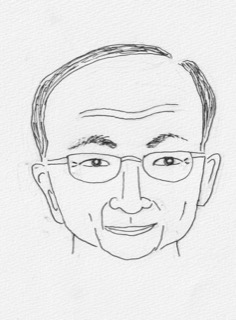
吉村 達彦(よしむら たつひこ)
1968年 トヨタ自動車工業(現・トヨタ自動車)入社
1988年 工学博士(東北大学)
強度実験課長・シャシー技術部長・信頼性強度機能主査等を歴任
2000年 九州大学 大学院工学研究院機械科学部門固体力学講座教授
2003年 General Motors Executive Director Reliability & Durability Strategy
2007年 ジーディーキューブコンサルティング代表
【受賞】
•自動車技術会論文賞
•機械学会技術貢献賞
•日経品質管理文献賞
【著書】
『トヨタ式未然防止手法GD3』(2002)日科技連出版
『想定外を想定する未然防止手法GD3』(2011) 日科技連出版
『想定外と言わない組織を作るAPATマネジメント』(2012) 日科技連出版
『発見力』(2016) 日科技連出版






