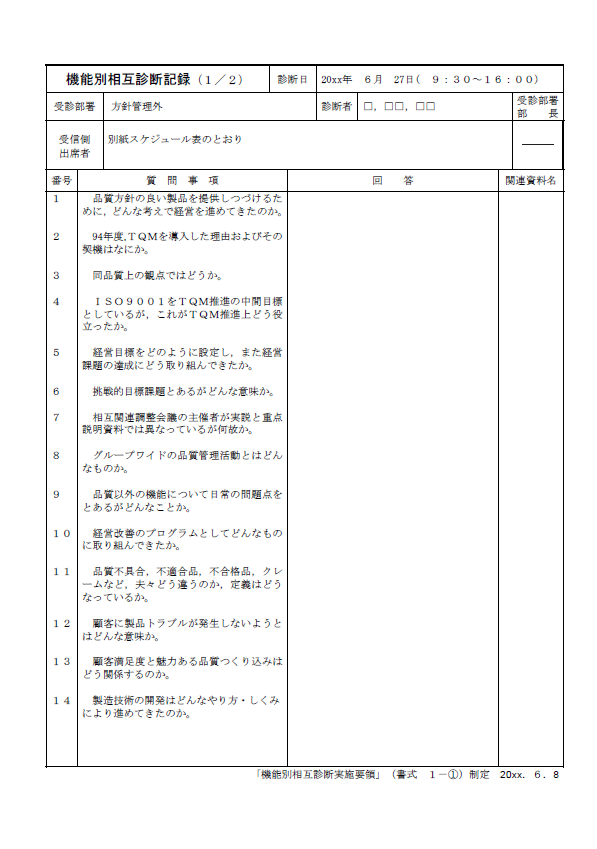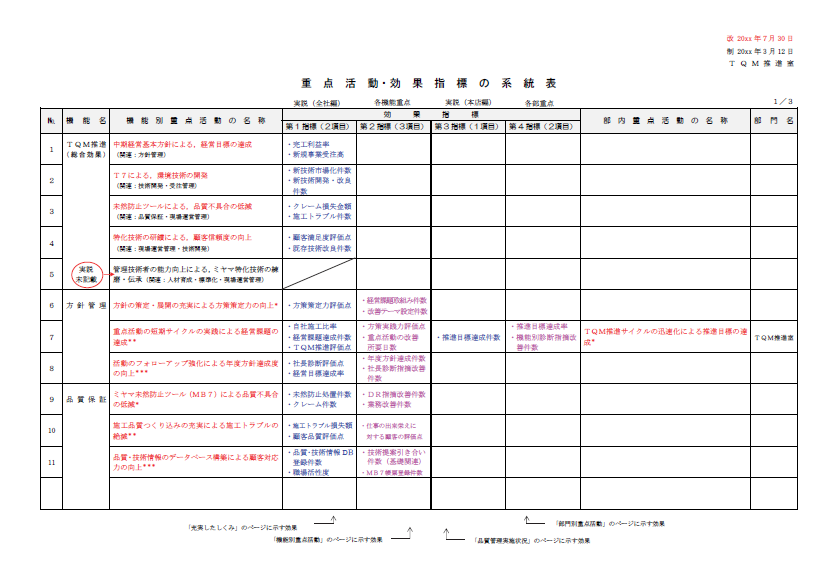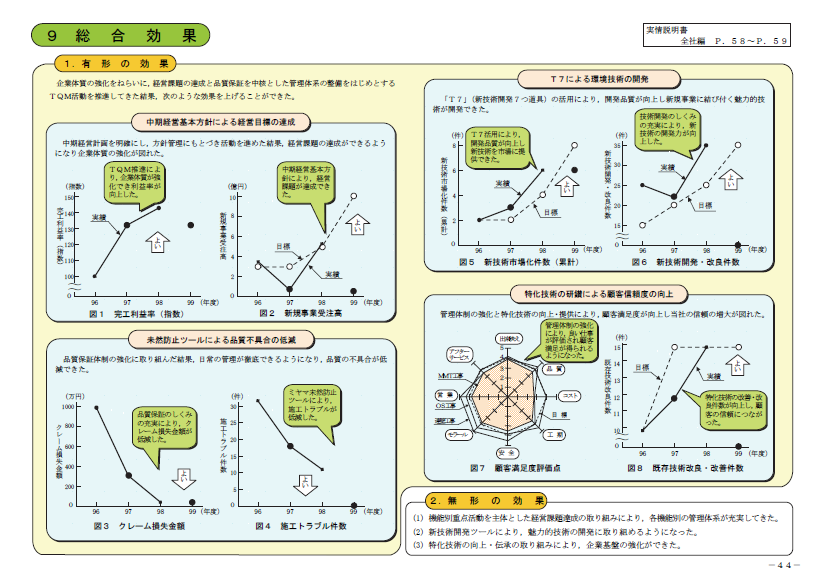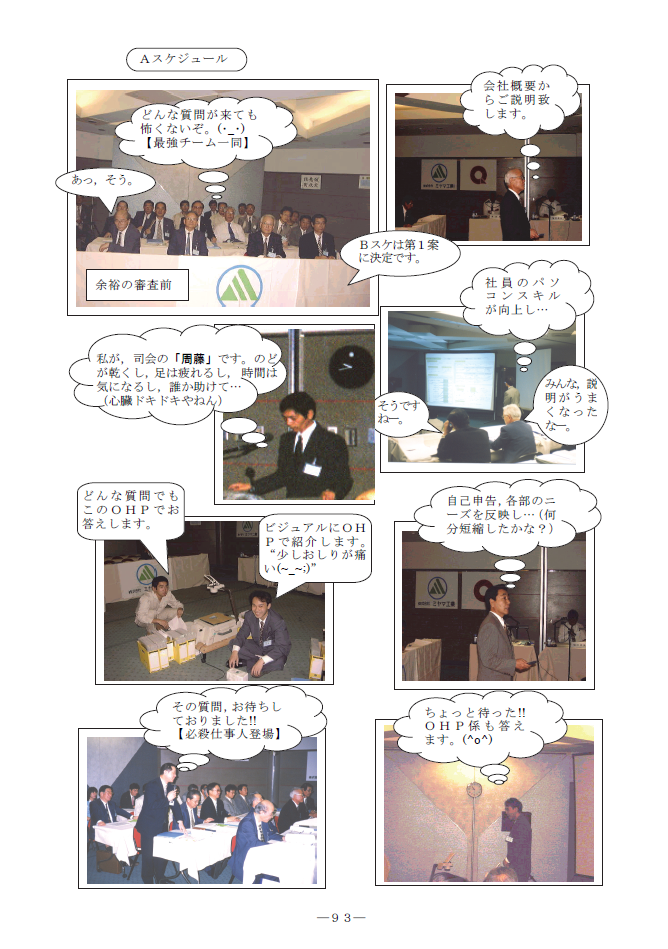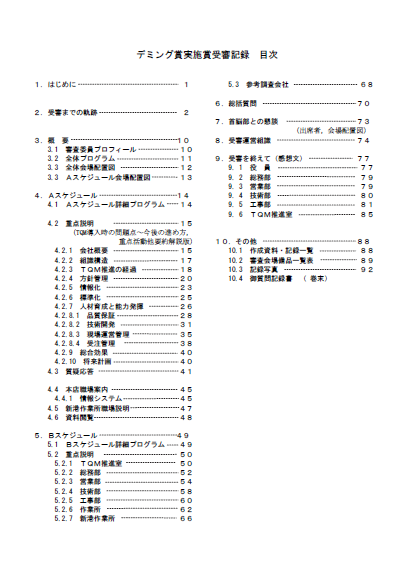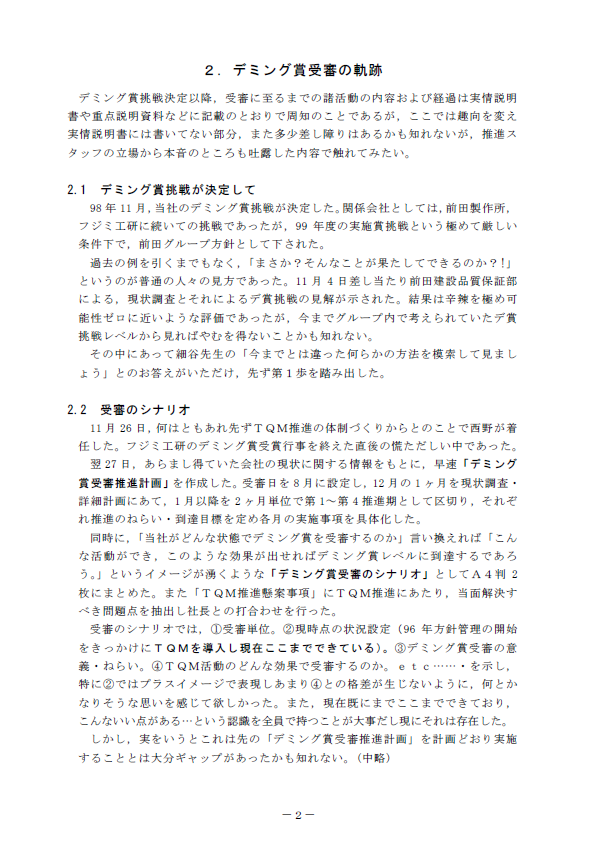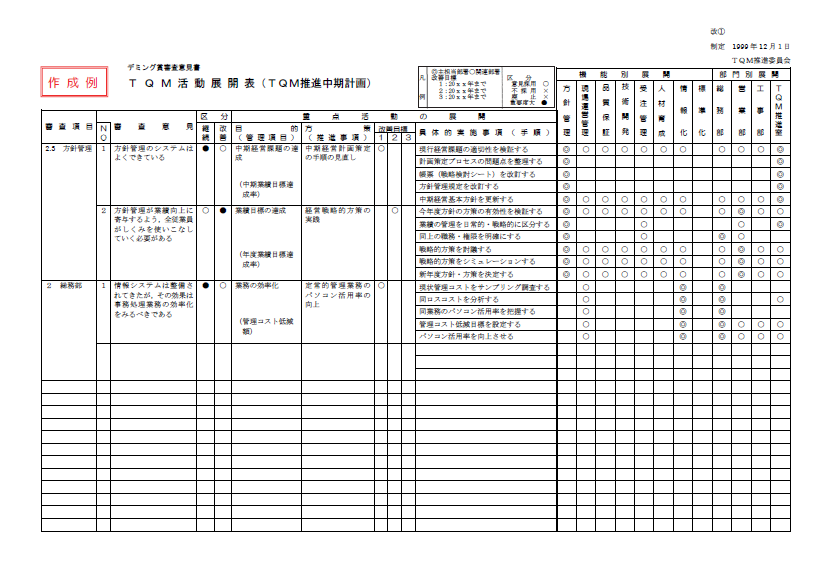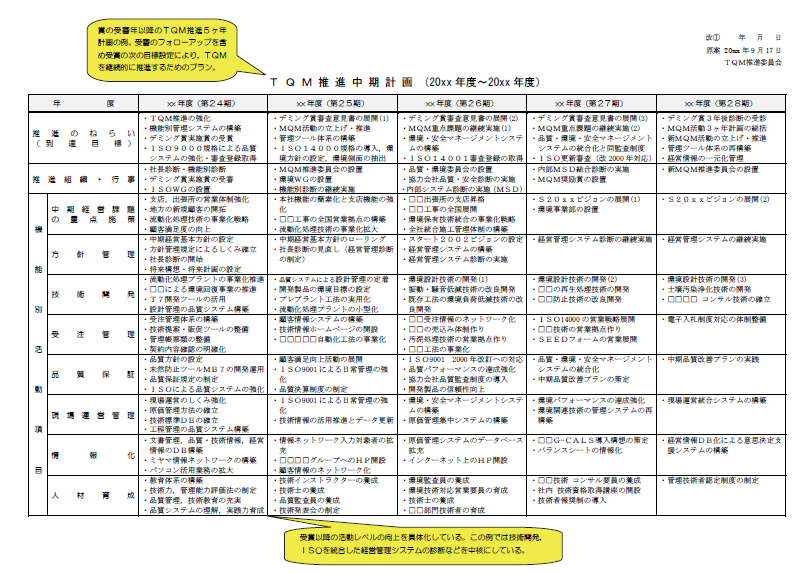TQM
企業の立場でTQM推進を思う―推進事務局の体験から―(最終号)<2016年03月24日>

今号が最終号になりました。
最初の投稿以来8回を数えましたが,TQM推進事務局の楽屋話に徹したつもりです。とりとめのないつまらない話に長い間お付き合いありがとうございます。
西野武彦 氏
1946年生まれ
1964年前田建設工業株式会社入社/以来,建築施工,TQM推進に従事
1989年同社デミング賞受賞
以降,グループ共全四社のデミング賞受賞,そのTQM推進事務局に従事, JSQC第1回品質管理推進功労賞受賞
現在,日本品質奨励賞審査員,ISO審査員(QMSエキスパート審査員),
品質管理学会員,TQM・ISO研修コース講師,一級建築士
著書:『品質経営システム構築の実践集』(日経品質管理文献賞受賞)
『超簡単!ISO 9001の構築』,
『ISO 9001プラス・アルファでパフォーマンス(業績)を向上する』
『ExcelでQC七つ道具・新QC七つ道具作図システム』
『Excelで統計解析システム検定・推定編/実験計画法編』ほか
何れも細谷克也共著,日科技連出版社
〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213
Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.