言語データの持つ可能性2<2015年10月16日>
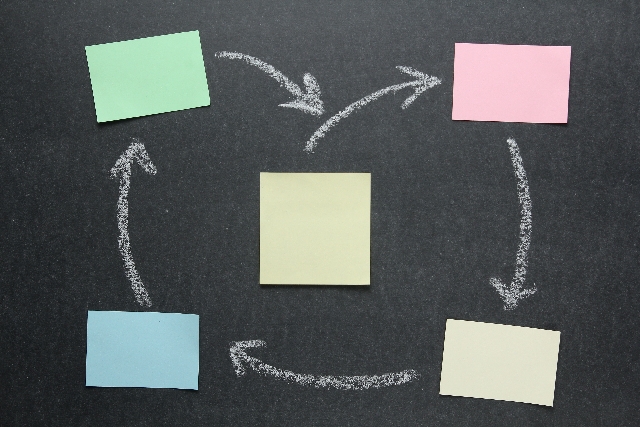
今日、「モノづくり」だけでなく「コトづくり」が重要だと言われてきています。
単にいいモノ、いいサービスは世の中にあふれており、改善により品質(当たり前の品質)向上をしても他社との差別化が難しくなってきています。このような時代では、「これまでにない新しいビジネスプロセス」など魅力的価値(魅力的品質)を生み出し、顧客の感性に訴えていくことが重要になります。新しい魅力的価値を生み出していく際には、新しい発想を得る思考方法を手助けするツールが必要不可欠です。
ここでマネージャ層の業務を考えると、新しい発想からあるべき姿を定義し、それを経営層に提案して理解していただき承認を得ていきます。さらに新しいあるべき姿をどのように実現していくか、部下と連携、引継して具体化、計画を検討していきます。
このようにマネージャ層では新しい発想を得るために思考を手助けするとともに経営層から部下まで幅広く立場を超えてコミュニケーションを取れるツールが必要となります。
ここで、改善活動で実績のある新QC七つ道具に着目すると言語データの関連性、構造を可視化し、そこから新しい発想を得てあるべき姿をまとめていくことが可能です。また、シンプルでわかりやすいルールにより、経営層から課員まで立場を超えて報告、説明するためのツールとしても非常に有効です。
これまではどちらかというと現場サイドで多く活用されてきた新QC七つ道具ですが、これからはマネージャ層でも新しい魅力的価値を生み出すツールとして活用されることが期待されます。
佐野 正樹
(デジタルプロセス株式会社
第一技術ソリューション部 次長SE)
学習院大学理学部数学科卒
1992年 デジタルプロセス(株)の前身である(株)日産システム開発へ入社。
入社以来、主として自動車、航空会社の開発プロセスで利用するシステムの企画、開発からサポートまでを手掛けるエンジニアとして従事。
セミナーへの参加をきっかけにN7とかかわり、自社での活用にとどまらず、N7部会への参加を通じてN7の活用範囲拡大に努めている。






