TQM
営業部門でTQMはどのように展開できるのか? アイホン 寺尾浩典常務に聞く(前編)<2017年10月11日>

(聞き手は、ジャーナリスト 伊藤公一 氏)
――貴社の主力商品のインターホンはそれを取り付ける住宅や施設の動きに左右されますが、昨今の市場をどう捉えていますか。
寺尾:需給の面から見ると、新築マーケットは長期的に縮小していくでしょう。国内の住宅市場全体では相続税法の改正に伴う影響で賃貸住宅の着工戸数が増えてはいますが、一時的な動きです。このため、戸建住宅では新築、リニューアルとも新商品の投入と積極的な仕様化、採用化活動に力を入れたいと考えています。
集合住宅については、新築マーケットの縮小を見越して以前から取り組んでいるリニューアル市場に着目した手を打っています。具体的には、豊富にある見積りストックやアフターサービス情報を生かして、分譲物件への活動を強化します。賃貸住宅では、それぞれの管理会社との関係を強めて、物件オーナーの要望を捉えた提案活動を進めていきたい。
――貴社の主力商品のインターホンはそれを取り付ける住宅や施設の動きに左右されますが、昨今の市場をどう捉えていますか。
寺尾:需給の面から見ると、新築マーケットは長期的に縮小していくでしょう。国内の住宅市場全体では相続税法の改正に伴う影響で賃貸住宅の着工戸数が増えてはいますが、一時的な動きです。このため、戸建住宅では新築、リニューアルとも新商品の投入と積極的な仕様化、採用化活動に力を入れたいと考えています。
集合住宅については、新築マーケットの縮小を見越して以前から取り組んでいるリニューアル市場に着目した手を打っています。具体的には、豊富にある見積りストックやアフターサービス情報を生かして、分譲物件への活動を強化します。賃貸住宅では、それぞれの管理会社との関係を強めて、物件オーナーの要望を捉えた提案活動を進めていきたい。
――貴社にとって住宅市場と並ぶ柱である病院や高齢者施設など、ケア市場の動きは。
寺尾:国策である地域包括ケアシステムという素地はあるものの、病院の着工件数の減少や高齢者施設への新規参入などで競争は激しさを増すばかり。このため、住宅同様、当社が培ってきた独自の技術やシステムで他社との違いを打ち出したい。その一環として、病院、施設ともに老朽化が進む旧来のナースコールシステムに代わる新型ナースコールシステムの提案活動に力を入れる計画です。例えば、ITを応用して電子カルテとも連携できるようにしたネットワーク活用型などは、需要拡大を促すのではないでしょうか。
■ デミング賞目指して奔走した若き日々
――貴社のTQM活動は常務がご担当の経営企画室を中心に進められていますね。
寺尾:組織的には各本部の上位に置かれていて文字通り経営をめぐる重要事項を司る部門です。いわゆる縦割りであったこれまでの体制を抜本的に見直したものです。かつては各本部から上がってくる案件をすべて社長が決裁していました。しかし、その方法には良い面もあればそうでない面もある。
そこで、全社的な立場で経営課題を抽出し提言する部門として2015年4月に経営企画室を新設し今年で3年目を迎えています。
――貴社のTQM活動は常務がご担当の経営企画室を中心に進められていますね。
寺尾:組織的には各本部の上位に置かれていて文字通り経営をめぐる重要事項を司る部門です。いわゆる縦割りであったこれまでの体制を抜本的に見直したものです。かつては各本部から上がってくる案件をすべて社長が決裁していました。しかし、その方法には良い面もあればそうでない面もある。
そこで、全社的な立場で経営課題を抽出し提言する部門として2015年4月に経営企画室を新設し今年で3年目を迎えています。
――常務は入社以来、ずっと営業畑を歩んでいらっしゃいますが、TQMとの関わりは。
寺尾:当社は1976年にTQCを導入し、1981年にデミング賞(中小企業賞)を受賞しています。私は1977年入社ですから入社
直後から4年間、このときのデミング賞受審に向けた準備に明け暮れました。何しろ、昨日まで学生だったから何も分からない。でも、分からないなりに必要な図表を作ったり、夜の打ち合わせのための買い出しに走ったりもしました。今振り返ると、この4年間は私を大きく成長させてくれたと思います。ですから、私の社会人としての原点はTQMにあると胸を張って言えますよ。
■ 環境変化に応じたTQM再活性化宣言
――貴社は2015年8月に「TQM再活性化宣言」を表明されています。ということは、いささか皮肉な言い方をすれば、かつては 盛り上がっていたわけですね。
寺尾:おっしゃるように、再活性化という以上、最初の活性化時代がありました。当社のTQCには40年余りの歴史があります。この間、当時の副社長が率いる推進室を設けたり、外部の先生方の指導を受けたりしてきました。しかし、年を重ねるごとにデミング賞を経験した人たちが少なくなってきた。それは、TQCやTQMをきちんと教えられる人材が少なくなってきたことを意味します。
その一方で、幸か不幸か、この時期の業績は右肩上がりだったので、差し迫った危機感を覚えることはありませんでした。QCサークル大会なども開いてきた。リーマンショックの影響からも比較的早く立ち直ることができました。そんな状態が続いたせいか、心ならずも、活動が形骸化してきたのです。
――社長が「宣言」を表明するに至った最大の要因はなんですか。
寺尾:要約すれば危機感と体質強化です。想像を超えるスピードで普及したスマホは大きな脅威となりました。下手をすれば、インターホンがいらなくなるかもしれない。主力商品がいらなくなれば、アイホンもいらなくなる。社員にも大きな不安を与えることになります。
そこで、指導の先生の助言もあってTQMを再活性化することにしました。今後の10年を見据えて仕事を見直し、全社の棚卸しをしようというわけです。活動を通じて、人材育成や組織強化にも取り組み、後の世代に引き渡す狙いもあります。
寺尾:要約すれば危機感と体質強化です。想像を超えるスピードで普及したスマホは大きな脅威となりました。下手をすれば、インターホンがいらなくなるかもしれない。主力商品がいらなくなれば、アイホンもいらなくなる。社員にも大きな不安を与えることになります。
そこで、指導の先生の助言もあってTQMを再活性化することにしました。今後の10年を見据えて仕事を見直し、全社の棚卸しをしようというわけです。活動を通じて、人材育成や組織強化にも取り組み、後の世代に引き渡す狙いもあります。
■ 指導できる体制をしっかり整える
――活動を進めるにあたって苦労した点はなんですか。
寺尾:これはもう明快。TQMを教える人材が決定的に足りないことです。「宣言」は2016年から18年までの3カ年計画の最重要項目の一つ。にもかかわらず、ほとんどの社員が日常の仕事の中でTQMを活用することなく、また指導できる人材も少人数でした。そこでTQMを推進する体制を整えTQMを指導できる人材を10人以上育成することにしました。1からと言うよりも、ゼロからスタートの覚悟です。
一方で、市川周作社長はじめ私も含め役員全員が日科技連のセミナーに参加し、他社や他業界の状況を見せていただきました。セミナーに参加し大変なショックを受け、改めてTQMの再活性化の必要性を強く感じました。そしてTQMの再活性化に対する機運を各本部、部門、部署などの末端の現場まで浸透させるため全社的に社長診断を推進することにしました。
――社長自らが強い意識をもって臨まれたことは大きな刺激になったのでは。
寺尾:すでにお話したような事情で、ほぼ全員が手探りの状態で恐る恐る前に進むという状況でした。これが正しい、という確固たる自信がないからです。文書を出してもらっても理屈が合わないので生きたものになっていない。提出された文書を添削して返し、再提出してもらう。そんなキャッチボールの繰り返しでした。
宣言後1年半の私見的達成度は70点。まったく何も知らなかった割にはよく漕ぎ着けたと思います。ただし、まだまだ受け身の構え。厳しい言い方をすれば、言われたことを数字にしているだけの面がある。改善テーマの一つです。
■ 新築案件とリニューアル案件の相違点
――営業部門におけるTQM活動の重点は。
寺尾:TQMに先立つビジネスの面からいうと、リーマンショック以降、新築の落ち込みをリニューアルが支えてきました。新築は物事の進め方や人脈が確立しているので、新規案件に臨むときには参考にすべき営業モデルがあります。ところが、リニューアルにはそのような前例や参考例がありません。ですから、まず、種をまくことから始めました。
仮に、今取り替えを提案しても、高額だし不要不急のものなので後回しにされます。その間に管理会社と根気よく交渉し、理解してもらう。そうして、積立金が貯まった3~5年後に実を結ぶという息の長い仕事です。
――営業部門におけるTQM活動の重点は。
寺尾:TQMに先立つビジネスの面からいうと、リーマンショック以降、新築の落ち込みをリニューアルが支えてきました。新築は物事の進め方や人脈が確立しているので、新規案件に臨むときには参考にすべき営業モデルがあります。ところが、リニューアルにはそのような前例や参考例がありません。ですから、まず、種をまくことから始めました。
仮に、今取り替えを提案しても、高額だし不要不急のものなので後回しにされます。その間に管理会社と根気よく交渉し、理解してもらう。そうして、積立金が貯まった3~5年後に実を結ぶという息の長い仕事です。
――同じ住宅案件なら新築とリニューアルとの連携ができるのでは。
寺尾:その通りです。設備機器としてのインターホンは新築であろうとリニューアルであろうと変わらないのだから、別々の仕事にするのは合理的ではありません。まず、新築の計画から納入までを一つの区切りとし、納入後にきちんとアフターメンテナンスして10年とか15年先を見越してリニューアルするサイクルを整える。それが新たな物件受注プロセス管理のシステムを導くのだと思います。
(後編へ続く)
・寺尾浩典氏 登壇のクオリティフォーラム2017詳細はコチラ
・寺尾氏登壇「営業部門における品質経営の進め方」セッションの趣旨は コチラ
寺尾:その通りです。設備機器としてのインターホンは新築であろうとリニューアルであろうと変わらないのだから、別々の仕事にするのは合理的ではありません。まず、新築の計画から納入までを一つの区切りとし、納入後にきちんとアフターメンテナンスして10年とか15年先を見越してリニューアルするサイクルを整える。それが新たな物件受注プロセス管理のシステムを導くのだと思います。
(後編へ続く)
・寺尾浩典氏 登壇のクオリティフォーラム2017詳細はコチラ
・寺尾氏登壇「営業部門における品質経営の進め方」セッションの趣旨は コチラ
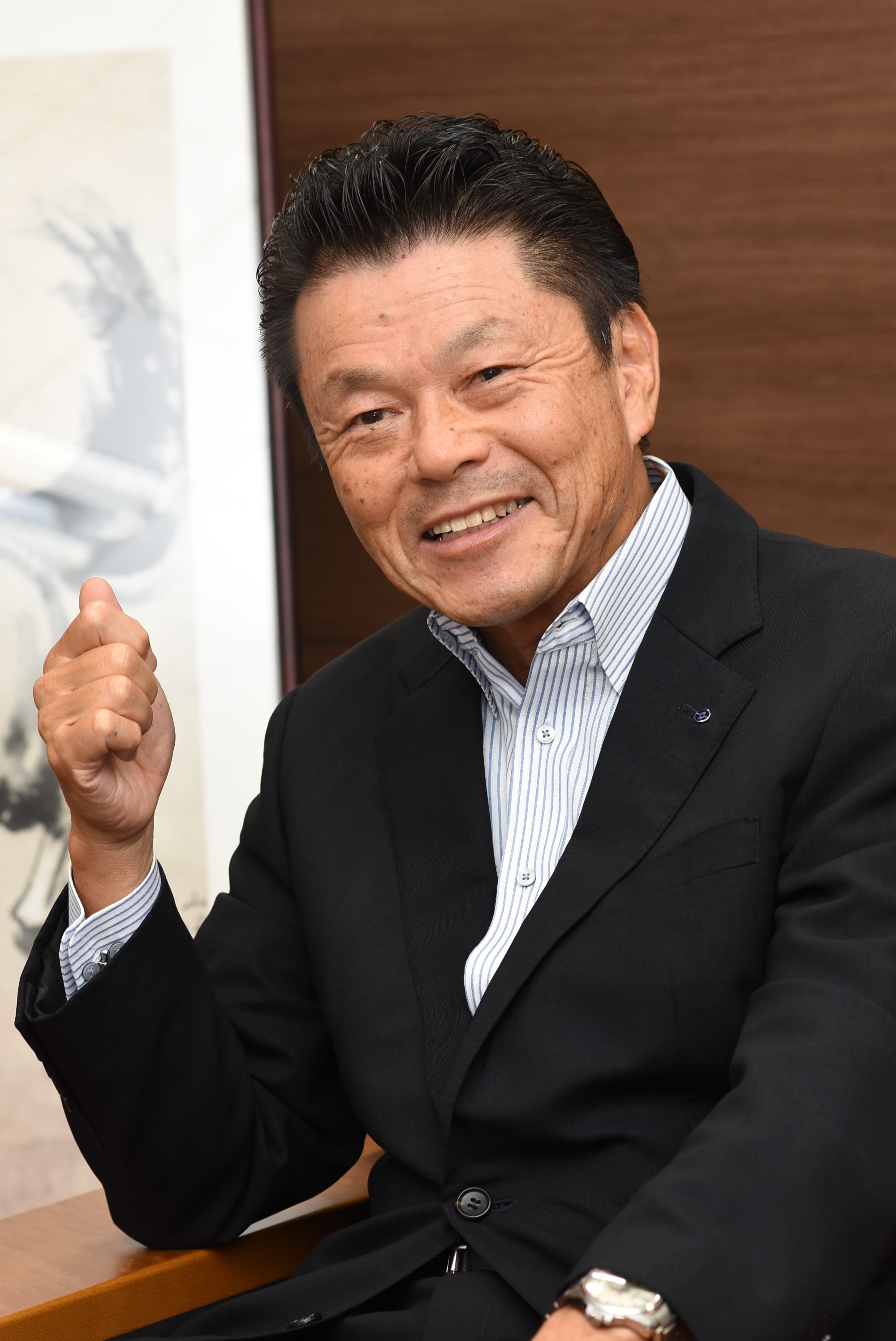
寺尾 浩典(てらお ひろのり)
アイホン 常務取締役経営企画室長。
1977年 アイホン株式会社入社。以後、2015年まで38年間営業畑一筋。
入社と同時にTQCの洗礼を受け1981年デミング賞受賞を経験。
神戸営業所所長、大阪営業所所長、大阪支店長等を経て、
2007年執行役員営業副本部長、2009年取締役営業本部長、2015年から現職。
〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213
Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.






