TQM
「未来の顧客価値」を起点にした新製品・サービス開発(2)<2015年07月15日>
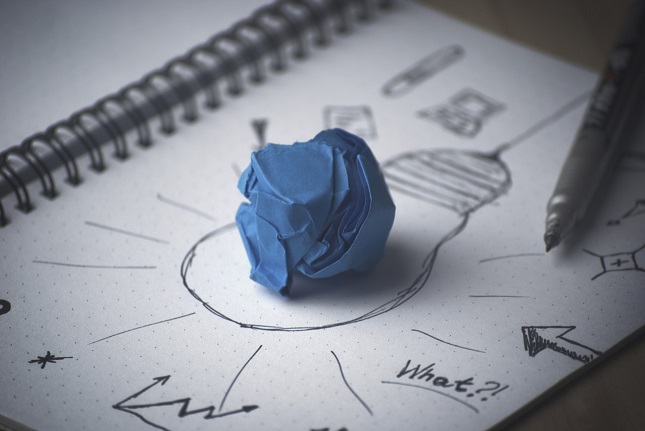
第1回では、「バックキャスティング」という新しい思考アプローチを紹介しました。バックキャスティングの特徴は、「未来」を起点とし、未来から逆算して「現在」を考えることにあります。一方、フォアキャスティングの発想は「いま」を起点にするため、企業が保有するシーズを活かして新たな価値を生み出そうとする場合、既に顕在化している不具合あるいは想定される不具合に着目した「改善系のアイディア」に終始する傾向があります。

図1 バックキャスティングの思考アプローチ
では、バックキャスティングの思考アプローチにすると、企業が保有するシーズの活かし方はどう変わるのでしょうか? 以下では、化粧品メーカーA社の取り組みを例にしながら、バックキャスティングの流れを紹介します。
(1)事業が目指す顧客の理想の策定
まず実施するのは、事業が目指すありたい姿を定めることです。A社の検討チームは同社の社史を振り返るなどして、「自分たちは事業を通じて人々の何を叶えたいのか?」という願いを事業コンセプトとして図2のように策定しました。

図2 A社の事業コンセプト
(2)リード・ユーザーの選定
次に、事業コンセプトに記した内容に関して、想定顧客の中で“他の誰よりも最前線で頑張っている人”(リード・ユーザー)を選定します。同社の検討チームは図3の選定理由をもとに、「産後育児中の元アナウンサー」をリード・ユーザーとして設定し、子供が小学校に入学するまでの6年間を中心に考えていくことにしました。

図3 リード・ユーザー選定理由
(3)与件の整理
リード・ユーザーが設定できたら、そのリード・ユーザーの周囲で起きること(外部環境の変化)を、PEST分析(*)の要領で整理します。その上で、リード・ユーザーの与件を導き出します。検討の結果、「自分たちの事業が着目すべきは『単に綺麗な肌』ではなく、その人に相応しい『その人に固有の表情』を創ること。表情というものは本人の内的状態(心の状態)に大きく影響される。その人に固有の表情づくりは、表情づくりのベースとなる『自らを感じる意識(自己意識)』にも目を向けて、そのような自己意識を顧客と共に育んでいくことが必要である」という考えに至りました。
*1 PEST分析:分析対象を取り巻く環境をP・E・S・T(Political=政治、Economic=経済、Social=社会、Technological=技術)の4つの側面に分け、それぞれを分析することにより、対象が外部環境からどのような影響を受けるのかを把握する手法。

図4 リード・ユーザーを取り巻く今後の外部環境と与件
(4)関わる範囲の設定
与件を踏まえ、リード・ユーザーに対するA社の関わり方(関わる範囲)を考えます。この関わる範囲とは、「新製品・サービスのアイディアを導出する際に、思考の対象とする範囲」と言う事もできます。別の言い方をすると、この関わる範囲から外れると「新製品・サービスの対象範囲」からも外れることになり、そこからアイディアが導出される可能性もゼロに近くなります。そのため、十分な注意が必要です。関わる範囲の設定とは、いわば「自分たちの事業の守備範囲」を宣誓することであり、自分たちの事業のアイデンティティを示すことといっても過言ではありません。そのため、このステップは非常に重要なステップだと言えます。
前のステップ(3)で述べたとおり、同社がリード・ユーザーと6年間にわたって向き合う際の最大の着眼点は「自己意識の高まり」です。リード・ユーザーは出産を機にそれまで活躍してきた社会から離れ、一時的に自己意識が大きく低下することが予想されます。そこでA社検討チームは6年間の月日に対し、自己意識の低下をいかに早期に食い止め(第1期)、自己意識を取り戻し(第2期)、そして6年後の新たな出発に向けて自己意識を高めていく(第3期)という3つの期を設定しました(図5 上段)。

図5 「関わる範囲の設定」と「新規要求項目アイディアの導出」
(5)新規要求項目アイディアの導出
関わる範囲の各期に対し、リード・ユーザーが要望するであろうことをリストアップします(図5 下段)。これらはまさに「将来の潜在ニーズのアイディア」といえます。これらの中から、「顧客からみた重要度」と「自社による実現可能性」、さらに、「当該リード・ユーザーに限らず多様なユーザーが今後のニーズとして顕在化させる可能性(=水平展開可能性)」という各観点から検討することによって、重点要求項目を絞り込みます。
(6)シーズの棚卸し
重点要求項目の実現に関わりうるシーズを棚卸しします。なお、ここでいうシーズには、「肌質別成分配合技術」や「高浸透技術」など各種技術、「肌状態計測システム」といったシステム、訪問販売員といった人的資源、それらの人的資源が持つノウハウなど、企業が保有する全ての知識が該当します。

図6 保有シーズの棚卸し
ここまでがバックキャスティングです。図7における「(1)「目指す姿」を起点として、自らの持ち物を見直し」がここまでのステップに相当します。そして、このあとに「(2)目指す姿の高度実現に向けて、シーズを価値化する」という段階に入ります。つまり、事業が目指す顧客の理想を実現するための手段としての「製品・サービス」を次々と考案します。

図7 バックキャスティング発想の価値創造
A社の検討チームの場合、肌を支える顔筋を細胞から創り込む「顔筋マッサージクリーム」や、顧客と設定した顧客自身の理想像に対して現在の進捗状況を顧客と一緒に管理する「協働モニタリングシステム」など計8つの新製品・サービスを考案するに至りました。これらの製品あるいはサービスは、顧客から見て個々に独立ではありません。これらは全て顧客の理想を実現する手段です。
昨今、商品レベルでの差別化の限界が指摘されています。各社の技術力の向上によって銘柄間の品質格差は小さくなっており、個々の製品あるいはサービスで競合に対する差別化を図ることは難しくなっていると言われています。待ち受けているのは、コモディティ化による激しい価格競争です。
しかし、個々の製品・サービスは独立ではなく、大目的を実現するために不可欠な手段であり、かつ、個々の手段の間には関係があるということになれば、話は別です。1つの手段が競合他社と似通っていても、顧客にとって重要なことは、自らの大目的を実現するための手段群を取り入れることであるため、手段同士に関係が認められれば特定の手段のみを切り出して競合銘柄にスイッチされてしまうリスクは下がることが期待されます。未来の顧客価値を起点としたバックキャスティングによる「新製品・サービスの継続的創造」とは、いわば新たなドメイン(カテゴリ)を創造していることであり、私はこれを「ドメイン・ブランディング」と呼んでいます。
今回紹介した新製品・サービス開発手法は「理想追求型QCストーリー」という名称がついており、図8のように実務家が自ら検討できるようワークシートを用意しました。未来の顧客価値を起点としたバックキャスティングの思考アプローチによる新しい手法を1社でも多くの企業のみなさまに活用いただきたいと思っております。

図8 理想追求型QCストーリー「実践ワークシート」

加藤 雄一郎 氏
(名古屋工業大学大学院 工学研究科 産業戦略工学専攻 准教授)
製造業、広告会社を経て、2003年に名古屋工業大学が国立大学初のMOT独立専攻を開設したことを機に転身。教鞭を執ると共に、「機会発見プロフェッショナルとして わが国の製造業に貢献する」をミッションとして研究室内に“Brand Design Lab”を立ち上げ、企業との共同研究、指導・支援にあたる。専門分野であるブランド戦略、マーケティング戦略などの他、近年はそれらとTQMの融合による、企業におけるブランド価値創造、経営システムの最適化手法の開発を進めている。
〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213
Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.






